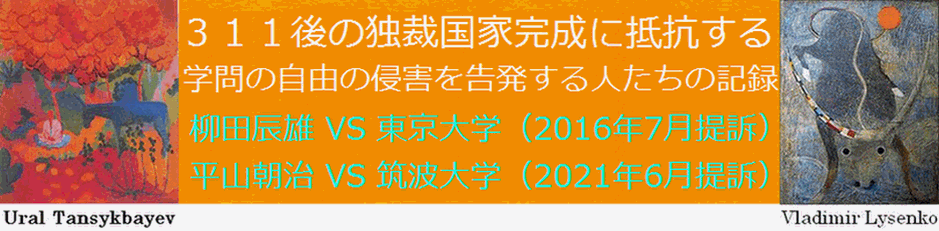※ 地裁判決に対する2審の控訴理由書->こちら
※ 本裁判2審の高裁判決->こちら
※ 本裁判の上告理由書->こちら そのエッセンスは->こちら
上告人代理人 柳原敏夫
2019年6月5日、薄い紙切れが最高裁から上告人代理人事務所に郵送されてきた。そこには、次の文句が書かれていた(紙切れ=最高裁決定の全文->こちら)。
たったこれだけ?!
私たちは、公文書偽造の真相を隠蔽した地裁判決(その批判は->こちら)とそれを追認した高裁判決(その報告は->こちら)に対し、可能な限りの異議申立(その全文は->こちら)を述べたのに、応答はこれだけ!!
ここには本件事件の生の事実、生の法律に触れた記述は一言もない。
あるのは、定型の決まり文句。
これなら、AIすら要らない。
1秒で完成。
楽チンだなあ。
こんな楽チンで済むというのは、実は司法は要らない、粗大ゴミだとみずから証明しているようなもの。それがこの決定の唯一の存在意義。
本件事件は東大の公文書偽造(正確には虚偽公文書作成。その文書は->こちら)という犯罪が問題になったのであり、原告は首尾一貫して、その真相解明を強く求めたのに、
裁判所がやったことは、結局、行政がやっていることには、それがスキャンダルであろうが犯罪であろうが余計な口を挟まない、黙って知らない振りに徹する。
それをするのが「いい子」なのだとしっかり躾けられている。
司法のピラミッドの頂点に立つ最高裁がこのザマだから、下々の高裁、地裁も右ならえで、みんなすっとぼけて黙って知らない振りをする。地裁から高裁、最高裁まで、全員東大の応援団。これに対し、原告の応援団席はほぼカラッポ。怖がって、研究者は誰も近寄らない。
その結果、東大の不正も司法がしっかり守ってくれると枕を高くして、これからも不正に励めることになる。東大は人事不正、研究不正の天国になる。
そして、本件事件の原告(学問の自由が侵害された東大教授)のような真面目な研究者ははじき飛ばされる。はじき飛ばされたくなかったら、何も知らない、見ない、聞かない振りをして沈黙の中に入るしかない。その結果、研究者って何? それは隠れキリシタンのことである、と再定義されるに至る。かくて、東大を頂点とする日本の研究機関は隠れキリシタンの全盛期を迎える。ここにはもう、学問の自由は存在しない。
学問の自由が存在しないところには、表現の自由も存在しない。 表現の自由が存在しないところには、民主主義も存在しない。これは私たち一人一人の市民の命、健康、自由が脅かされるという問題だ。
知は誰のものか?--学問の自由の侵害を訴えた本件事件が根本的に問うたことはこれである。原発事故を経験するまで、原発の科学技術という知は原発を推進・管理する国家のもの、電力会社のもの、原子力推進の研究者たちのものと考えて疑わなかった。しかし、いざ原発事故で深刻な生命の危機を経験してみて、私たちは、原発の科学技術という知は何よりもまず私たち市民のものなんだと痛切に悟らされた。本来「知は市民のもの」だとしたら、知を研究する研究者は何よりも第1に、市民に対する説明責任を果すこと、市民に対して誠実であることが求められる。
言い換えれば、研究者は国家や大学等による介入、干渉により、「自ら行っている学問研究について市民に対して誠実であり、説明責任を果すこと」が歪められてはならない。これが研究者に「学問の自由」が保障される根本の理由である。
学問の自由が国家や大学等により侵害されたとき、その回復を図ることを本来のミッションとする司法がそれを全くせず(ちょっとでも検討した痕跡すら残さず、一刀両断に問答無用と切り捨てた)、その反対にひたすら行政のお墨付きを与えるパピードッグに堕してしまったことは、三権分立の内部崩壊であり、民主主義の深刻な危機である。
「司法の独立」の危機はひとり香港だけではない、日本も同様なのだ。
以下は、「 司法の独立」の危機を自ら身をもって体験した原告自身による最高裁決定に対するコメントです(そのPDF->こちら)。
**************
2019年6月10日
柳田辰雄VS東京大学「学問の自由」侵害裁判の上告審における
2019年6月4日最高裁判所第三小法廷上告棄却等の決定に対するコメント
上告人(控訴人・原告) 柳田辰雄
本裁判は、日本における司法の行政からの独立、裁判制度のガバナンスすなわち統治と自治を検証するものとなりました。言い換えるならば、東京地方裁判所、高等裁判所と最高裁判所における裁判を通じて、民事裁判における裁判員制度の導入が必要であると痛感しました。
官僚裁判官制度の下では、裁判における判決は、官僚が運営している行政側の意向を忖度したものとなり、司法制度の行政からの独立はありえません。
これが、日本の裁判制度の現状です。
1945年、日本は敗戦により太平洋戦争を終結させました。そして、1952年、アメリカ合衆国をはじめとする連合国諸国と間の戦争状態をサンフランシスコ平和条約の発効により、日本は、連合国諸国との「戦争状態」を終結させました。
この期間に、アメリカ政府は新たな日本の裁判制度を成立させましたが、司法組織が行政から独立して機能する仕組みは制度化されませんでした。なぜなら、行政組織としての連合国最高司令官総司令部が日本の行政組織を管理するために、官僚裁判官という制度の下での司法制度は都合が良いからです。
ところで、東京大学憲章では「その決定と実践を厳しい社会の評価にさらさなければならない」としていますが、憲法で定める「学問の自由」への制度的保障として大学自治が与えられているとしても、ある一つの講座における研究分野のあらたな選定が、将来の社会の公益性と関係しており、社会と没交渉ということはありえません。大学院の専攻における教育研究において、各講座は専攻内の教育研究の責任を明確にし、教授のそれぞれの専門分野における責任を明確にして当該分野における教育研究を究めることを主な目的として導入されています。したがって、それぞれの講座は、大学院が組織的に教育研究を行っていくために、各々の教員が自立して役割を分担しながらも組織的な連携を確保し、責任の所在を明確化するために制度化されなければなりません。
東京大学大学院新領域創成科学研究科は、学融合を基本理念に、領域横断的な研究を対象とすることを目的として新設された学部をもたない独立した研究科です。したがって、新設するにあたっては、東京大学の学内外で基礎的あるいは先端的な研究分野を専門としている教員を募って発足しています。
このような社会状況の中で、国際社会の様々な問題を社会科学の「学融合」という全体論的に、すなわち、研究対象を社会における相互依存と相互関係として総合的および包括的に理解し、諸問題を解決するための提言をしようと構想されたのが新領域創成科学研究科の国際協力学専攻です。
学融合(トランスディシプリナリー)を社会科学方法論の超越科学として、1978年に著作において紹介されたのは西部邁東大教養学部助教授でした。そして、1983年には、この東大教養学部を礎として大学院総合文化研究科に設立されています。この学融合(トランスディシプリナリー)という社会科学方法論は、当時の教養学部の社会科学科で提唱されていた学際的(インターディシプリナリー)を超えて、類似の社会科学的な方法論により社会全体の動きを捉えられない限り、社会科学の社会における存在意義は限定的なものになるという着想によるものでした。
このような東京大学における社会科学の方法論の歴史的な展開の中から、国際協力学専攻の制度設計講座は、社会科学の「学融合」により全体論的な方法論から、総合的および包括的に人類の国際社会の問題を理解し、その解決の糸口を捉えようとしていました。
特に、制度設計講座の国際政策協調学は法、経済学および政治学に基づいて、これら学問の学融合のうえに全体論的に、各国の立法、司法および行政の統治と自治を検証します。さらに、この検証に基づいて、グローバルガバナンス、すなわち国際システムの「国際共治」を研究する分野として企画・構想されています。
大学院大学における教育研究の基本の組織は、講座にあります。研究分野の変更はこの講座の存続に関わっており、大学における自治と学問の自由の基本に関わっています。
今回の訴訟の根幹には、制度設計講座の唯一の教授であった私の意見や講座の構想を無視して、専門分野を異にする他の講座の教授達の内規から外れた手続きで、研究分野を選定して教授人事が行われたことにありました。
以 上